|
トップ
|
|
|
■ 寄棟の屋根
|

(1)
|

(2)
|
LEC は、いうまでもなく茅葺き屋根(1)ですが、屋根の形としては、四方から棟(頂の稜)に向けて傾斜部が寄せているので寄棟(よせむね)という名前になります。
これとは対照的に、棟の両側のみ傾斜がある屋根を切妻(きりづま)と呼びます。
また、切妻と寄棟を合せた入母屋(いりもや)という形など、屋根にはいろいろなバリエーションがあります。
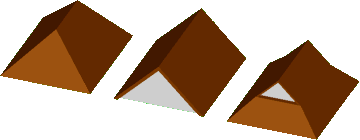
左から 寄棟/切妻/入母屋
|
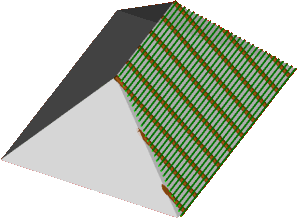
縦の茶色が垂木/横の緑が棧
|
|
さて、LEC の屋根は、今から約20年前に、雪で前半分の一部が脱落したため、葺き替え作業を行ないました。
そのときは、西宮からも、ローバーやスカウトクラブが駆け付け、茅の刈り取りから、葺き替えの作業の一部を手伝いました。
当時の記録が残っていれば、また紹介したいと考えますが、残念ながら、私は残していません。
さて、葺き替え作業では、まず茅を、秋に刈り取ります。
冬、スキー場になるところが、茅場です。
刈った茅は、冬の間乾燥させ、春に葺き替え作業を行ないます。
茅を葺く前は、もちろん屋根を裸にするのですが、茅を剥いだ屋根は、籠のようになっています。
垂木(たるき)を縦に渡し、さらに横に棧(えつり)と呼ばれる竹を置きます。
その上に束ねた茅を載せていくのです。
今も、屋根裏(2)を見ると、その籠の形を窺い知ることができます。
屋根裏や土蔵には、刈った茅が保存されています((2)の右端)。
補強などに使うために残してあるのだと思いますが、京都では毎年少しずつ貯めて、小屋裏が一杯になったら葺き替えるそうです。
なお、屋根裏には、機織り機のような道具も置かれています。
|
|
|
■ 軒
|

(1)
|

(2)
|
茅葺きでは、茅の、葉の方を下にするでしょうか、根元の方を下にするでしょうか。
これは、茅葺きの世界では、常識中の常識で、根元の方が下、が正解です。
軒の写真(1)を見てください。
確かに根元の茎が見えているでしょう。
逆にするのは、逆葺きといって、水車小屋や船小屋など、簡略な建造物に限られているのです。
根元を下にするのは、耐久性のためだということです。
実際、冬の、つららが軒に下がった様子を見ると(2)、軒には十分な強度が必要に感じます。
|
|
|
|
しかし、根元を下にすると、面倒なことになります。
葉の、細い方が上になるので、積めば積むほど傾斜が緩くなってしまうのです(3)。
|
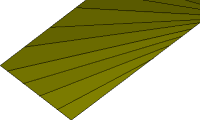
(3) 軒部分断面
|
このため、軒を作るには、最初に垂木の先端に茅負(かやおい)という太い竹を横たえ、そこに丈夫な短い茅を選んで、軒付けという端の部分をガッチリこしらえ、その上に茅を積んでいきます。
また、茅の先の部分に捨て茅という詰め物をしながら、押え竹で押えつつ茅を何層にも積んで、厚みを作るそうです(4)。
|
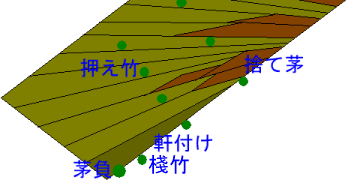
(4)
|
|
軒は智恵の固まりです。
|
|
|
■ 棟の文字
|
|
|
棟(むね)は、両側から積み上げた茅が来てぶつかるところですが、最後の部分で茅は V字形の谷間を作ります。
ここの部分をしっかり埋めないと、雨漏りがしますし、風の影響も受けます。
そこで、この部分だけは、トタンの小さな屋根をかぶせているわけです。
|

(1)
|

(2)
|
|
先に述べた 20年前の葺き替えのときは、記念にここに「レック」の文字(1)を入れました((2)は文字部分の拡大)。
縁側から外に出て、屋根を見上げれば見つけることができます。
|
|
|
■ 破風の文字
|
|
|
棟の三角形の部分、これを破風(はふ)といいますが、LEC はこの部分に、くずし字で 龍 と書いてあります(1)。
同じような文字は、池原周辺の家々に見られ、家紋であったり、寿 の文字が書かれていたりします。
ちなみに、小倉さんの家は 寿 でした。
ところで、LEC の 龍 は、諏訪神社の神様でもありますが、この場所に書くのは、龍の水神としてのご利益にあずかろうという気持ちです。
つまり、これは、火伏せ(ひぶせ)といって、水に関係あるものを屋根に置いて(書いて)、火事から建物を守ろうとするおまじないなのです。
|

(1)

国宝 二条城二の丸御殿 の 懸魚
|
火伏せは、文字だけでなく、シャチホコやシビのような魚を屋根に置くこともありますし、懸魚(げぎょ)という、魚の尾をした飾りを破風に付けることもします。
昔の人にとって、火事は大変恐ろしいものでしたから、おまじないででも、災難から身を守ろうとしたのですね。
実際、茅葺き屋根の家は、燃える物ばかりで作られていて、燃え出したが最後、すぐに燃え尽きてしまうでしょう。
|
|

(2)
|
ところで、龍 の反対の破風には何と書いてあるでしょう。
ずばり、水(2) です。
分かりやすいおまじないですね。
|
|
|
■ 墨書
|
|
|
(1)にある板の墨書には、LEC の建物がいつ誰によって建てられたかが書かれています。
|

(1)
|
|

|
拡大した左の写真でも判読しにくいので、以下に内容を記します。
|
明治廿一年(*1)旧七月廿七日
午前二時頃燃始
午前四時焼滅ス
火元 嘉兵衛 茂三郎 庄助
仝年仝月仝日
午後四時頃始メ
杣(*2)棟梁 當村 田原弥市
越後國西頸城郡下根知村大字上野(*3) 安田安エ門
并に
大工棟梁 當村 山田喜三郎
立主 小倉庄助 庄助トハ繁松ノ事也
家立 明治廿一年旧九月貮拾一日より貮拾三日迄
|
|
(*1) 明治廿一年 = 明治21年 = 1888年
(*2) 木こり。今では材木屋ですね。
(*3) 現在の糸魚川市上野(うわの)のことと思われます。ごく近くに大工屋敷という地名もあります。
|
|
火伏せのおまじないをするほど、火事を怖れていても、この LECも建て替える前は、火事で焼失したのでした。
それで建て替えたのが、明治21年。
その墨書きのある板を他から移したのでなければ、この建物は 築113年 ということになりますね。
|
|
LEC について調査すると、もっといろいろ発見があるかも知れませんよ。→ ベンチャーの諸君。
トップ
|
